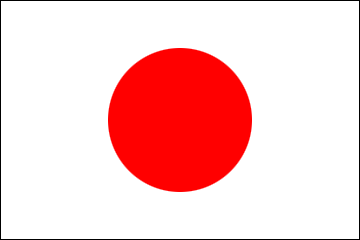日本文化と中国文化
平成28年4月12日
本日は、日本文化の特徴について、中国文化との違いにも言及しながら、お話したいと思います。しかしながら、そもそも、文化とは極めて広い概念であり、限られた時間の中で全てを話しことは到底不可能です。そこで、今日の聴衆の皆さんは若い人達ですので、簡単に日本文化の歴史的な背景を説明した上で、三つのテーマ、(1)漢字文化 (2)食文化 (3)日本人の礼儀作法についてお話をします。
1.日本文化の源流
●皆さんご存じの通り、2000年以上も昔、日本は中華文明の影響を強く受けました。政治・社会制度だけではなく、思想、哲学、宗教、食文化、芸術など、ほぼ全ての分野にわたって中国の文化を吸収しました。
●しかしながら、9世紀以降、中国の文化を基礎としつつも、徐々に日本独自の文化も発展させてきました。吸収と消化が日本文化の特徴と言えますが、日本と中国との間では、以下のような違いが見られます。
(1)まず、季候・風土が異なること。
中国は、基本的に大陸国家であり、農業も盛んですが、少数民族(騎馬民族)による牧畜も発展しました。一方、日本は、基本的に農耕民族であり、農業は皆で協力する必要があります。また、島国で海洋国家であり、また、森の国でもあります。台風、地震など大きな自然災害も多いわけですが、一方で温暖な季候は多くの自然の恵みももたらしました。
(2)二つ目は民族の違いです。
日本人のルーツについては、学問的にも未だ詳しいことは分かっていませんが、シベリア方面の北方、朝鮮半島経由、さらに東南アジアなど、各方面から様々な民族が渡ってきたと言われています。中国大陸からもかなり多くの人達が来たと思われますが、大多数の日本人の遺伝子は漢民族と異なります。因みに、日本人の血液型の40%はA型です。
(3)三つ目は、宗教面での違いです。
古代において、中国から儒教、仏教、道教などの宗教・哲学が日本に伝わりました。これらは、今日においても、日中両国の共通の文化的な基盤となっています。しかしながら、これらの宗教・哲学が日本に伝わる以前、古代の時代から、日本では、無数の神様が信仰されてきました。
2.漢字文化
●言語も文化を反映する大きな要素です。日本語はモンゴル語や韓国語などと同じく、ウラルアルタイ語族に属しており、その文法は中国語とは大きく異なりますが、今でも約2000の漢字を常用漢字として政府が選定しています。常用漢字とは、新聞、書籍などを読むことを含めて日本人の日常生活において必要とされる漢字です。
●大多数の漢字は中国語と同じ意味ですが、一部には中国と違い意味のものもあり、日本語学習者にとっては注意を要するところです。
例えば、
暗算→小学生などが学校で習う「心算」のことです。
階段→楼梯 台阶
恰好→外表,姿势
怪我→受伤
勉強→学习,用功
こうした例は数多くあります。また、非常に意味は似ているが、微妙な違いがある、あるいは使い方が違うといった語彙も沢山あります。こうした違いを良く理解していないと、コミュニケーション上、不必要な誤解を生じるおそれがあります。
●また、日本語に以下のような特徴があります。
(1)敬語の表現が極めて多いこと。
日本人は、言葉を用いる人が相手や周囲の人、また、その場の状況に合わせて、「敬い」「憊くだり」などを表現します。日本語を勉強する外国人にとっては、極めて難しい難関ですが、日本人でも完全にマスターできていない人がいます。幾つか簡単な例を紹介します。
(ア) ある人が知り合いの家に電話をかけたとき:
「恐れ入ります。お父様はご在宅でしょうか。」「实在不好意思,您父亲在家么?」
「父は、まだ帰宅しておりません。」「我爸还没回来」
(イ) 人にプレゼントを渡す時
「つまらないものですが、どうぞお受け取り下さい。」「无聊的东西而已,请收下吧」
人を自宅に招いて食事する時
「何もありませんが、どうぞお召し上がり下さい。」「什么也没有,请」
(2)曖昧な表現が多いこと。
(ア) 多くの場合、主語が省略されます。
「お元気ですか」 「(你)好吗」
「よろしくお願いします」 「请多关照」
「ただいま」(私は、ただ今、帰りました。) 「回来了」(我回来了)
「いただきます」 「开始吃了」
(イ) 断定的な言い方を避け、婉曲的な表現を多く使います。
「善処します」 「妥善处理」
「考えておきます」 「再考虑一下」
「タバコはご遠慮下さい」 「关于吸烟,请多考虑一下」(禁止抽烟)
3.食文化
(1)「和食・日本人の伝統的な食文化」→ユネスコの無形文化遺産
(ア) 多様で新鮮な食材と素材の味わいの活用
日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根ざした多様な食材が用いられています。
(イ) カロリーが低くバランスの良い健康食
日本の食事スタイルは栄養バランスが良く理想的だと言われています。また、動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿、肥満防止に役立っています。
(ウ) 多様な調理法と調理道具
切る、煮る、焼く、蒸す、揚げるなど多様な調理法があります、また、素材の味わいを生かす調理技術・調理道具が発達しています。
(エ) 自然の美しさの表現
季節の花や葉などで料理を飾り付けたり、季節に合った調度品や器を利用するなど、四季の移ろいは季節感を大事にします。
(オ) おもてなしの心
日本人の食文化は、民族の年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。
(2)日中の食事マナーの違い
食事に関するマナーに関しては、日中間で多くの違いがあります。例えば、
(ア) お酒を飲む時、中国では必ずお互いに乾杯しますが、日本では自分一人で飲むことも多くあります。
(イ) ご飯茶碗、吸い物・味噌汁のお椀は必ず手に持って飲みます。日本料理ではスプーンは使いません。
食事に関する一番大きな違いは、食事の分量でしょう。中国では、必ず食べきれないほど多くの料理が出され、客が残せば、「もう、お腹いっぱい頂きました」ということで主人も満足するようです。日本では、客がちょうど食べきれる量を考えて料理を作ります。
4.マナー
(1)個別の違いを紹介する前に、マナーに関係があると思われる文化的な背景を少し話したいと思います。
まず、儒教の影響です。儒教は非常に深遠な哲学・宗教だと思いますが、同時に、「礼」、つまり、しきたり、マナーを重視しました。今日、この影響は、韓国に一番強く残っていると思いますが、日本でも、冠婚葬祭のしきたり、年長者に対する敬意などの面で一定の影響があります。
(2)もう一つ提起したいのは、「謝罪」つまり、謝ることについての考え方です。現在の日本は法治国家ですが、伝統的には、例えば、ある人が大きな間違いを犯した際、心から謝罪すれば、許してあげるとの考え方があります。一方、多くの日本人は、中国では、間違えを認めることは、すなわち、それに応じた責任を取る、場合によっては、金銭的な賠償責任が必然的に生じると聞かされています。だから、中国人は簡単には謝らない、あるいは、中国では簡単に謝ると大変なことになると言われています。本当にそうでしょうか?私は、こうした言い方はあまり正しくないと思います。約10年前、私は、浙江省にある「抗日記念館」を見学しました。その際、館長は「自分たちは、日本側に賠償を求めているのではない。日本側の誠実な謝罪を求めているだけだ。」と言いました。
(3)最後に、個別のマナーについて、二つの例を挙げて日中両国の違いを紹介します。
(ア) まずは、「挨拶」です。
どこの国でも、特に初対面の時の挨拶は大変重要で、色々な礼儀作法があります。ご存じのとおり、日本の場合は、お互いに「お辞儀」を交わしますが、「お辞儀」は他の国ではあまり見かけません。相手との関係などによって「お辞儀」の角度、丁寧さの度合いもことなります。
また、社会人同士であれば、通常、名刺交換を行います。もちろん、現在は、中国でも名刺交換を行いますが、日本人の場合は、まず、顔を合わせると直ぐに名刺交換し、相手が所属する会社あるいは団体名、肩書などを確認した後、丁寧にお辞儀をします。
日本人がそうした礼儀にかなりこだわるのは、相対的に、日本社会では、出身地、卒業した学校、あるいは、所属する会社、団体にこだわる傾向があります。
(イ) もう一つは、日本人は、乗り物などで老人などにあまり席を譲らないとの指摘です。残念ながら、基本的はその通りだと思います。昔はかなりちゃんと譲っていたと思いますが、最近では、あまり譲りません。譲らない側の考え方としては、電車・バスには老人、身体障害者、妊婦などの専用である「優先座席」があるので、そこに座れば良い。老人の場合、相手の年が分からないので、もしかしたら、「俺はまだ老人ではないと、怒られるかもしれない。」妊婦に見える女性は、もしかしたら、「単に太っているだけかもしれない」など、色々なことを考えてしまいます。因みに、私は、青島に来てから、バスに乗るとすぐ席を譲られますが、心の中では「ああ、自分も本当の老人になってしまった」と思います。また、街角では、小さい子供から「爷爷」と呼ばれて、最初はショックを受けました。これも日中の文化の違いだそうです。中国では、60歳以上の人を「叔叔」と呼ぶのは、失礼だそうです。
1.日本文化の源流
●皆さんご存じの通り、2000年以上も昔、日本は中華文明の影響を強く受けました。政治・社会制度だけではなく、思想、哲学、宗教、食文化、芸術など、ほぼ全ての分野にわたって中国の文化を吸収しました。
●しかしながら、9世紀以降、中国の文化を基礎としつつも、徐々に日本独自の文化も発展させてきました。吸収と消化が日本文化の特徴と言えますが、日本と中国との間では、以下のような違いが見られます。
(1)まず、季候・風土が異なること。
中国は、基本的に大陸国家であり、農業も盛んですが、少数民族(騎馬民族)による牧畜も発展しました。一方、日本は、基本的に農耕民族であり、農業は皆で協力する必要があります。また、島国で海洋国家であり、また、森の国でもあります。台風、地震など大きな自然災害も多いわけですが、一方で温暖な季候は多くの自然の恵みももたらしました。
(2)二つ目は民族の違いです。
日本人のルーツについては、学問的にも未だ詳しいことは分かっていませんが、シベリア方面の北方、朝鮮半島経由、さらに東南アジアなど、各方面から様々な民族が渡ってきたと言われています。中国大陸からもかなり多くの人達が来たと思われますが、大多数の日本人の遺伝子は漢民族と異なります。因みに、日本人の血液型の40%はA型です。
(3)三つ目は、宗教面での違いです。
古代において、中国から儒教、仏教、道教などの宗教・哲学が日本に伝わりました。これらは、今日においても、日中両国の共通の文化的な基盤となっています。しかしながら、これらの宗教・哲学が日本に伝わる以前、古代の時代から、日本では、無数の神様が信仰されてきました。
2.漢字文化
●言語も文化を反映する大きな要素です。日本語はモンゴル語や韓国語などと同じく、ウラルアルタイ語族に属しており、その文法は中国語とは大きく異なりますが、今でも約2000の漢字を常用漢字として政府が選定しています。常用漢字とは、新聞、書籍などを読むことを含めて日本人の日常生活において必要とされる漢字です。
●大多数の漢字は中国語と同じ意味ですが、一部には中国と違い意味のものもあり、日本語学習者にとっては注意を要するところです。
例えば、
暗算→小学生などが学校で習う「心算」のことです。
階段→楼梯 台阶
恰好→外表,姿势
怪我→受伤
勉強→学习,用功
こうした例は数多くあります。また、非常に意味は似ているが、微妙な違いがある、あるいは使い方が違うといった語彙も沢山あります。こうした違いを良く理解していないと、コミュニケーション上、不必要な誤解を生じるおそれがあります。
●また、日本語に以下のような特徴があります。
(1)敬語の表現が極めて多いこと。
日本人は、言葉を用いる人が相手や周囲の人、また、その場の状況に合わせて、「敬い」「憊くだり」などを表現します。日本語を勉強する外国人にとっては、極めて難しい難関ですが、日本人でも完全にマスターできていない人がいます。幾つか簡単な例を紹介します。
(ア) ある人が知り合いの家に電話をかけたとき:
「恐れ入ります。お父様はご在宅でしょうか。」「实在不好意思,您父亲在家么?」
「父は、まだ帰宅しておりません。」「我爸还没回来」
(イ) 人にプレゼントを渡す時
「つまらないものですが、どうぞお受け取り下さい。」「无聊的东西而已,请收下吧」
人を自宅に招いて食事する時
「何もありませんが、どうぞお召し上がり下さい。」「什么也没有,请」
(2)曖昧な表現が多いこと。
(ア) 多くの場合、主語が省略されます。
「お元気ですか」 「(你)好吗」
「よろしくお願いします」 「请多关照」
「ただいま」(私は、ただ今、帰りました。) 「回来了」(我回来了)
「いただきます」 「开始吃了」
(イ) 断定的な言い方を避け、婉曲的な表現を多く使います。
「善処します」 「妥善处理」
「考えておきます」 「再考虑一下」
「タバコはご遠慮下さい」 「关于吸烟,请多考虑一下」(禁止抽烟)
3.食文化
(1)「和食・日本人の伝統的な食文化」→ユネスコの無形文化遺産
(ア) 多様で新鮮な食材と素材の味わいの活用
日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根ざした多様な食材が用いられています。
(イ) カロリーが低くバランスの良い健康食
日本の食事スタイルは栄養バランスが良く理想的だと言われています。また、動物性油脂の少ない食生活を実現しており、日本人の長寿、肥満防止に役立っています。
(ウ) 多様な調理法と調理道具
切る、煮る、焼く、蒸す、揚げるなど多様な調理法があります、また、素材の味わいを生かす調理技術・調理道具が発達しています。
(エ) 自然の美しさの表現
季節の花や葉などで料理を飾り付けたり、季節に合った調度品や器を利用するなど、四季の移ろいは季節感を大事にします。
(オ) おもてなしの心
日本人の食文化は、民族の年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである「食」を分け合い、食の時間を共にすることで、家族や地域の絆を深めてきました。
(2)日中の食事マナーの違い
食事に関するマナーに関しては、日中間で多くの違いがあります。例えば、
(ア) お酒を飲む時、中国では必ずお互いに乾杯しますが、日本では自分一人で飲むことも多くあります。
(イ) ご飯茶碗、吸い物・味噌汁のお椀は必ず手に持って飲みます。日本料理ではスプーンは使いません。
食事に関する一番大きな違いは、食事の分量でしょう。中国では、必ず食べきれないほど多くの料理が出され、客が残せば、「もう、お腹いっぱい頂きました」ということで主人も満足するようです。日本では、客がちょうど食べきれる量を考えて料理を作ります。
4.マナー
(1)個別の違いを紹介する前に、マナーに関係があると思われる文化的な背景を少し話したいと思います。
まず、儒教の影響です。儒教は非常に深遠な哲学・宗教だと思いますが、同時に、「礼」、つまり、しきたり、マナーを重視しました。今日、この影響は、韓国に一番強く残っていると思いますが、日本でも、冠婚葬祭のしきたり、年長者に対する敬意などの面で一定の影響があります。
(2)もう一つ提起したいのは、「謝罪」つまり、謝ることについての考え方です。現在の日本は法治国家ですが、伝統的には、例えば、ある人が大きな間違いを犯した際、心から謝罪すれば、許してあげるとの考え方があります。一方、多くの日本人は、中国では、間違えを認めることは、すなわち、それに応じた責任を取る、場合によっては、金銭的な賠償責任が必然的に生じると聞かされています。だから、中国人は簡単には謝らない、あるいは、中国では簡単に謝ると大変なことになると言われています。本当にそうでしょうか?私は、こうした言い方はあまり正しくないと思います。約10年前、私は、浙江省にある「抗日記念館」を見学しました。その際、館長は「自分たちは、日本側に賠償を求めているのではない。日本側の誠実な謝罪を求めているだけだ。」と言いました。
(3)最後に、個別のマナーについて、二つの例を挙げて日中両国の違いを紹介します。
(ア) まずは、「挨拶」です。
どこの国でも、特に初対面の時の挨拶は大変重要で、色々な礼儀作法があります。ご存じのとおり、日本の場合は、お互いに「お辞儀」を交わしますが、「お辞儀」は他の国ではあまり見かけません。相手との関係などによって「お辞儀」の角度、丁寧さの度合いもことなります。
また、社会人同士であれば、通常、名刺交換を行います。もちろん、現在は、中国でも名刺交換を行いますが、日本人の場合は、まず、顔を合わせると直ぐに名刺交換し、相手が所属する会社あるいは団体名、肩書などを確認した後、丁寧にお辞儀をします。
日本人がそうした礼儀にかなりこだわるのは、相対的に、日本社会では、出身地、卒業した学校、あるいは、所属する会社、団体にこだわる傾向があります。
(イ) もう一つは、日本人は、乗り物などで老人などにあまり席を譲らないとの指摘です。残念ながら、基本的はその通りだと思います。昔はかなりちゃんと譲っていたと思いますが、最近では、あまり譲りません。譲らない側の考え方としては、電車・バスには老人、身体障害者、妊婦などの専用である「優先座席」があるので、そこに座れば良い。老人の場合、相手の年が分からないので、もしかしたら、「俺はまだ老人ではないと、怒られるかもしれない。」妊婦に見える女性は、もしかしたら、「単に太っているだけかもしれない」など、色々なことを考えてしまいます。因みに、私は、青島に来てから、バスに乗るとすぐ席を譲られますが、心の中では「ああ、自分も本当の老人になってしまった」と思います。また、街角では、小さい子供から「爷爷」と呼ばれて、最初はショックを受けました。これも日中の文化の違いだそうです。中国では、60歳以上の人を「叔叔」と呼ぶのは、失礼だそうです。