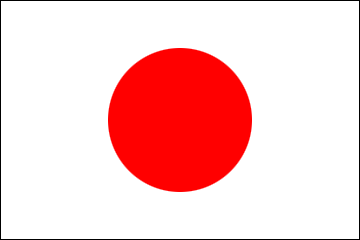康有為故居の訪問
令和7年7月28日
先日、斎藤総領事は青島市内にある康有為の故居を訪問しました。康有為は清朝末期、日本の明治維新を参考に体制内改革を推進しようとした戊戌変法のリーダーとして有名です。康有為はもともと広東省出身ですが、70歳で没するまで最後の数年間を青島のこの館で過ごしました。
戊戌変法に失敗した後、康有為は世界中を放浪しますが、日本は初めての海外の地であり、その後も含め計三度ほど滞在しています。4番目の妻となった市川鶴子ともこの間に出会っています(館内に関連の写真あり)。清末民初のこの時期、日本には中国から大勢の留学生や亡命者が集まり、日本の政治家や財界と損得勘定を越えた友情を育み深い交流があったことが今に語り継がれています。これらの中では特に孫文・黄興・章炳麟らが有名ですが、康有為も後に首相となる犬養毅らと深い親交があったことなどで広く知られています。
康有為は2回目の青島滞在となった1923年、以前ドイツ提督副官の住居だったこの場所を購入しました。小魚山の南麓に位置し、当時は海の眺めも良かったようで、家族への手紙で「上海よりも良いところ」と絶賛したそうです。現在青島の代名詞となって いる「紅い瓦、緑の木々、碧色の 海、青い空」というフレーズも、館内の説明によれば康有為が(初めて)口にしていたのではないかと思われる節があります。
自宅で最後を迎えた康有為の墓は、当初別の場所にあったようですが、1985年に現在の浮山の南麓に移設されました。中国の近代化に向けた激動の時期を駆け抜けた康有為は、時代が近いこともあり、日本の近代化(明治維新)に向けて活躍した幕末志士の人生を彷彿させるものがあります。そんな人物の足跡を辿り感傷に浸ることのできる場所が青島にもあることは幸いだと感じています。
戊戌変法に失敗した後、康有為は世界中を放浪しますが、日本は初めての海外の地であり、その後も含め計三度ほど滞在しています。4番目の妻となった市川鶴子ともこの間に出会っています(館内に関連の写真あり)。清末民初のこの時期、日本には中国から大勢の留学生や亡命者が集まり、日本の政治家や財界と損得勘定を越えた友情を育み深い交流があったことが今に語り継がれています。これらの中では特に孫文・黄興・章炳麟らが有名ですが、康有為も後に首相となる犬養毅らと深い親交があったことなどで広く知られています。
康有為は2回目の青島滞在となった1923年、以前ドイツ提督副官の住居だったこの場所を購入しました。小魚山の南麓に位置し、当時は海の眺めも良かったようで、家族への手紙で「上海よりも良いところ」と絶賛したそうです。現在青島の代名詞となって いる「紅い瓦、緑の木々、碧色の 海、青い空」というフレーズも、館内の説明によれば康有為が(初めて)口にしていたのではないかと思われる節があります。
自宅で最後を迎えた康有為の墓は、当初別の場所にあったようですが、1985年に現在の浮山の南麓に移設されました。中国の近代化に向けた激動の時期を駆け抜けた康有為は、時代が近いこともあり、日本の近代化(明治維新)に向けて活躍した幕末志士の人生を彷彿させるものがあります。そんな人物の足跡を辿り感傷に浸ることのできる場所が青島にもあることは幸いだと感じています。